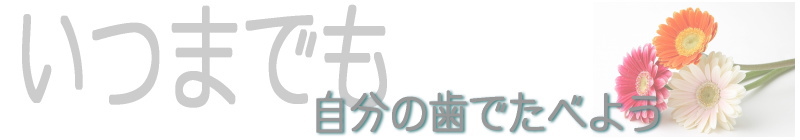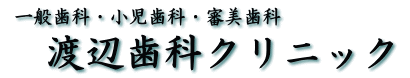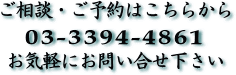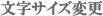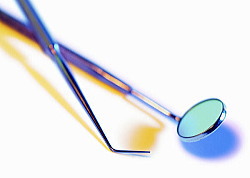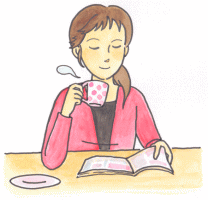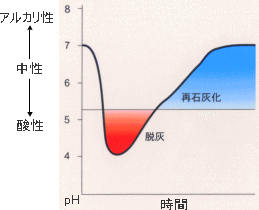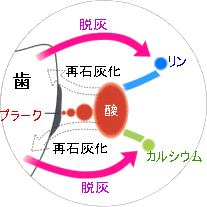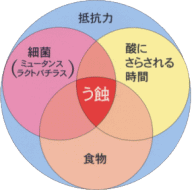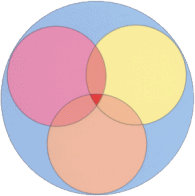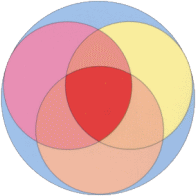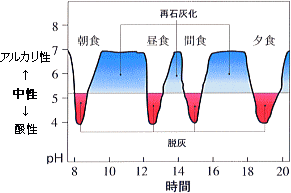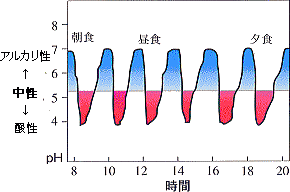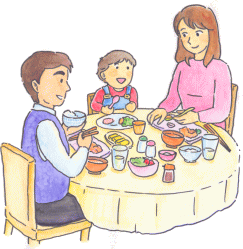| 杉並区下井草の歯科医院、長年の信用と技術の歯医者・歯科医院(渡辺歯科クリニック) |
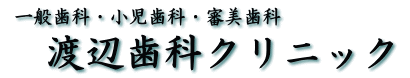 |
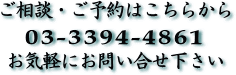
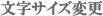    |
| (杉並区、下井草)貴方のかかりつけの歯科医院、人に優しく患者さまの立場に立ったクリニック |
|
|
|
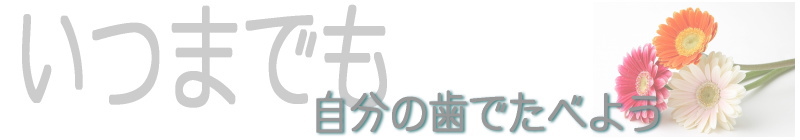 |
HOME  歯のお話し 歯のお話し  虫歯のメカニズム(脱灰と再石灰化) 虫歯のメカニズム(脱灰と再石灰化) |
|
|
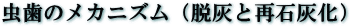 |
同じように食事をしていても、虫歯になる人とならない人がいるように、虫歯になる人には原因があります。
このページでは健康な歯がムシ歯になる初期メカニズムを簡単にご説明します。虫歯の発生メカニズムをよく理解してお口の中の状態を常に健康に保つよう気を付けましょう。 |
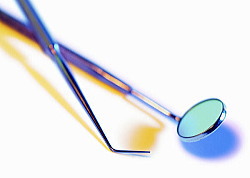 |
|
|
|
| 脱灰と再石灰化 |
お口の中では、食事や飲み物を摂取して3分ほどで虫歯の活動が始まろうとします。
一番悪いことをするのがお砂糖です。 |
 |
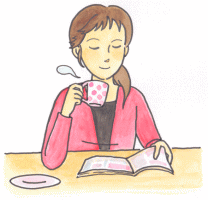 |
これらを摂取しますと、歯面にくっ付いている歯垢(プラーク:Pluqe)の中ではバイ菌により酸が作られます。酸性度が歯を溶かす程度(Ph5〜7)になると、歯の表面からミネラル成分、カルシュウムやリンが溶け出します。(図2)
この状態を脱灰(だっかい)と呼びこれが虫歯の活動の始まりです。 |
しかし、食後しばらくすると唾液の力(酸を中和、きれいに洗い流す作用)等により歯垢(プラーク)やペーハー(Ph)は中性方向に向かい、唾液中のミネラルが戻りはじめ、虫歯の出来やすい環境から出来にくい環境へ戻り始めます。この状態を再石灰化(さいせっかいか)と呼びます。(グラフ1)
|
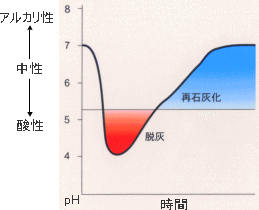 |
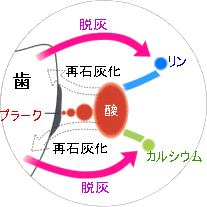 |
| (グラフ1) |
(図2) |
このように、お口の中では食事の後に虫歯が活動し始めたり、治ったりしています。 参考まで、摂取した糖度が高いほど、唾液の力や量が弱いほど再石灰化への時間が長くかかります。
一番大切なことは、常にお口の中を再石灰化しやすい状況にもって行くことがなによりも重要です。ではどうすればよいのでしょうか? |
|
| 虫歯になる条件 |
| 虫歯は細菌と食物と酸にさらされる時間、更に抵抗力の組み合わせで起こります。 真ん中の赤い部分が大きいほど、虫歯になるリスクが高いことになります。 |
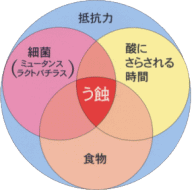
|
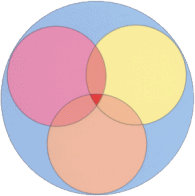 |
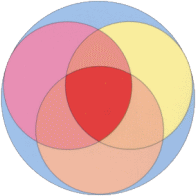 |
| リスクが低い |
リスクが高い |
先ほども書きましたが、食事をとると、口の中は酸性になり(phが低くなり)歯の表面の成分であるカルシュームとリンが溶かされはじめます(脱灰)。ふつうならば食後40分程度でphは高くなり、溶かされたカルシウムやリンは元にもどり再石灰化され始めます。 しかし、酸にさらされる時間や回数が多いと、歯の脱灰がつづき、虫歯が進行していきます。
つまり、虫歯が出来る要因には食生活にも大きく関係があるといえます。 |
| 以下のグラフでは食事や間食のタイミングと脱灰・再石灰化の関係を表しています。上記円グラフ同様赤い部分が多いと虫歯になるリスクが高くなるといえます。 |
食事をとるたびに、お口の中は数分で酸性となり(phが低くなる)、歯の表面の成分(カルシウム・リン)がとけはじめます(脱灰)。
但し、40分ぐらいたつとphは高くなり、とかされた歯の成分はもとにもどされ再石灰化されます。 |
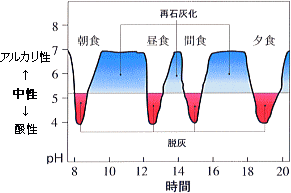 |
しかし、食べ物を口にする回数が多いと、酸性の状態が長くなり、歯の成分がもとにもどる時間がなく、虫歯ができるリスクが一段と高くなります。
特に寝る前の飲食は就寝中は唾液分泌量が少なくなるため、再石灰化は起こりませんので、更に虫歯へのリスクが高まりますので注意が必要です。
|
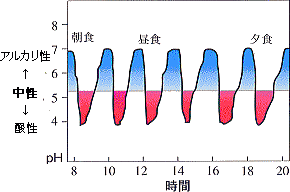 |
脱灰により悪い状態が続き、歯の内部構造まで至る穴が開いてしまったら、残念ながら治療の対象となります。 脱灰→再石灰化を繰り返すそのプロセスに対して、再石灰化を促すより良い環境を整えることが一番重要です。
このような、脱灰→再石灰化を繰り返すプロセスを良く理解して食生活そのものから見直すことも大切といえます。 |
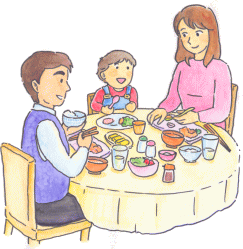 |
|
|
|
|
|
 TOP TOP |
|
Copyright (C) Watanabe Dental Clinic All Rights Reserved. |